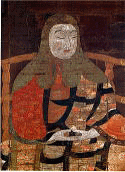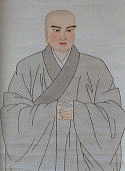宗祖は言われるだろう「あなたも菩薩の一人として、
浄仏国土顕現のために力を尽くしてください」と。
天台宗の教えのエッセンスは、まさに大乗仏教の精神をわし掴みにするものです。
それは、自らが完全なる利他的存在となるべく仏陀を目指す「菩薩」という生き方。
人間には本来、自他の区別を忘れて一切を同じように愛しく思う性質が備わっており、
すべての人がそのすばらしい性質を発揮するなら、この世界こそが浄土となる。
宗祖伝教大師はこの着想の実現に生涯をかけられ、後世に願いを託して入滅されました。
その願いは1200年余りを経た今日もなお、私たちを鼓舞し続けています。
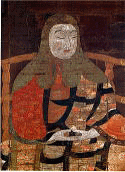 |
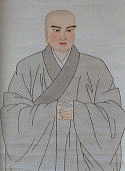 |
| 宗祖伝教大師 |
高祖天台智者大師 |
| 名 称 |
天台宗(天台法華円宗) |
| 総本山 |
比叡山延暦寺 |
| 高 祖 |
天台智者大師(智顗)=中国天台宗開祖 |
| 宗 祖 |
伝教大師(最澄) |
| 本 尊 |
久遠実成無作の本仏をもって本体とする。諸仏はこの本仏が
縁に随って現れた応現の身であるから等しくこれを尊信する。 |
| 経 典 |
根本経典「妙法蓮華経」を中心とするすべての大乗経典。 |
| 教 義 |
法華一乗の教意にて円・密・禅・戒・念仏を融合し実践する。 |
人生はまさに苦悩と不安の連続です。しかし、そうした経験は私たちに「正しい生き方」を求めるきっかけを与えてくれることも事実です。仏教ではその答えを精神の最高の変容状態としての「仏」に求めていくわけです。仏の主な性質は一切をありのままに知る「智慧」と、すべてのものを救おうとする利他の「慈悲心」であるといわれます。そして、これら2つの性質は互いに深く影響しあっていて、コインの表裏のように切り離すことのできないものなのです。智慧を確かなものにするためには利他の行いによる功徳の蓄積が不可欠であり、利他の心は智慧を深めるにしたがってさらに増大していくのです。このように、その性質を最大限に高めていくことによって、私たちは仏と等しくこの世界に調和をもたらすものとなることができます。一人ひとりの存在が世界の平和と幸福の源泉となりうるのです。もし、このような考えに触れて心に喜びを覚えるならば、あなたはすでに仏の道を歩み始めているといえるでしょう。
先に述べたような志をもって修行を続ける人を「菩薩」と呼びます。菩薩は大乗仏教の特徴的な人格であり、その修行の目的は小乗仏教の修行者のように自らの解脱を得るためではありません。彼らの最大の関心事は自分自身より、むしろ全体の幸福にあるのです。それゆえ、菩薩はその修行によって無限に他者を救済することのできる完全な利他的心身(=仏)を求めるのです。利他が動機であり目的でもある菩薩にとっては、仏となることさえ手段にすぎないわけです。このような考えに基づく仏教の系統は、偉大な乗物によってすべてのものを救っていく教えとして「大乗仏教」と呼ばれています。天台宗の宗祖である伝教大師最澄上人は、この大乗の教えを日本に根付かせるために比叡山延暦寺を開かれました。日本人の性質というものが大乗精神を受容するのに相応しい器であると考えられたのです。人々が共に助け合い、分かち合い、互いに幸福を願いあえる社会は現代の私たちの理想でもあります。いまから1200年前、伝教大師は菩薩的人材こそが「国宝」であると述べられ、その育成に生涯を費やされました。この国がいずれ菩薩たちで満たされ、浄仏国土となることを真摯に願われたのです。
天台宗ではすべての大乗経典を大切にしていますが、とりわけ「妙法蓮華経」を根本経典として尊信しています。この経典において釈尊は、仏は人々の違いに応じてさまざまに教えを説くけれども、それらに普遍する法(真理)は同じであり、どの教えによっても「完全なる仏陀の悟り」という一つの乗物に導かれるのだと明かされます。また、仏教教団最大の反逆者として知られるダイバダッタでさえ、将来は仏となって多くの人々を教化するのだと告げられるのです。この法華経の視点に立てば、仏の教えに触れたものはいかなる者でも、またいかなる形式の教えに依拠しようとも、いずれは必ず菩薩の道を経て仏となるのであり、何ひとつとして切り捨てられるべきものはないということになります。この思想が「法華一乗思想」であり、天台宗の思想的根幹をなすものです。伝教大師は法華経が説くこの一乗思想に立って、すべての法門を融合させた仏教というものを模索されました。その結果、比叡山は円教・密教・禅・戒律・念仏すべてを実践する仏教総合大学となったのです。こうして、すべての人の成仏を説き、一切の法門を内包する比叡山には多くの人材が集まり、鎌倉時代にはその門下から道元・栄西・法然・親鸞・日蓮などがそれぞれ一宗を起こす偉業を成し遂げられたのです。
仏教では事物がそれぞれ独立した実体として存在している、という見解を否定します。それは、ひとつの網が無数の網目に支えられてはじめて成り立つように、この世界の一切は他に支えられて存在しているからです。この構造は「縁起」と呼ばれ、仏教諸派に貫流する主題です。そして、縁起しているものはすべて他に依存して「仮」に現れているにすぎないので、本来生滅増減もなければ色形の区別もない、つまり「空」なのです。「空」を観じることは「空観」とよばれ、私たちを日常的な見方が引き起こす「我」の捉われから解放してくれます。しかし、この見方に固執すれば事物は実在しないというニヒリズムに陥ります。そこで、縁によって現れている「仮」の姿をもう一度見るのです。これを「仮観」といって、事物個々の特質を再認識し、他に対する無関心を防ぐのです。この2つの見方は視点が異なるだけで同じ対象を捉えているのですが、聖性と凡性を別々にしか照らせないという欠点があります。事物の正しい観察はこの2つを同時に見る「中道観」によってはじめて達成されるのです。天台宗ではひと思いのうちに一切を空と観じ、仮と観じ、また空仮が一であると観じる「一心三観」を指南としています。
「一心三観」を修していくと、一切の事物は法界(時間を含む全宇宙)が縁に従いその総体をあげて映し出している一焦点であり、一々に歴然とした特質を有しながらもその内容はまさしく同体であると知らされます。個々がお互いを完全に具えあい、しかも自在に融通しあっているその全運動こそが法界の姿だと知るのです。ここにおいて、見る主体と見られる客体を隔てる壁は消え去ります。目の前に散りゆくひとひらの花びらは、いまそれを見ている私や万象すべての一焦点として、過去・現在・未来の諸相をもすべて具えながら悠久の姿として散っているのです。一切は互いに具えあい、円に融けあっている。これが「円教」と呼ばれる、天台宗の教えなのです。我も他も、善も悪も、凡夫も仏もすべてその外に出るものはありません。したがって、この円教のなかに完全に座り込んでしまえば、悟るために改めて断つべき迷いもないことになります。円教による成仏は迷いを捨てるのではなく、ただ転じることで凡夫のままに仏となるとして「転迷開悟」という言葉で表わされます。
「円頓戒」とは円教の理念に基づき、僧俗を一貫する菩薩の戒法として創出された実践行のひとつです。その骨子は、仏の活きた万徳を直接仏から授けていただくというものです。この仏の徳は「戒体」という名で呼ばれ、これを受け取るとたとえ幼年であっても王位を継承すれば国王となるように、私たちも直ちに諸仏と同等の有資格者となるのです。また、円頓戒を受けると内なる能力が活現され、自然と次の戒めに親しむようになるとされています。①摂律儀戒(しょうりつぎかい=一切の悪を行わない)②摂善法戒(しょうぜんほうかい=すべての善を進んで行う)③摂衆生戒(しょうしゅじょうかい=利他に努める)。①については細目として重軽併せて五十八の禁戒があり、僧俗共にそれらすべてを授けられるのですが、保つ分に関しては各々の任意とされます。それはこの戒があくまで「一切の悪を行わない」という意志を重視するものであり、利他の動機に基づく菩薩の主体的な行動を一々規定するものではないからです。受戒者は仏によって約束された未来の仏であり、自らそれを自信し、行為の一々が全体の幸福に繋がるようつねに願いながら日々を生きてこそ、天台宗の教えの実践者ということができるのです。
ルンビニーの園でお生まれになった釈尊は天地を指差し「天上天下唯我独尊」といわれたとされています。この逸話をどのように解釈するかは人によって異なるでしょうが、釈尊が他者との比較において自らの権威を示されたと考えたのではつまりません。興味深いのは未だ成道に達していない乳児の釈尊がこの言葉を発せられたということです。これまでのなかで、私たちはみな全宇宙を備える存在だということをお話してきました。それは、一人ひとりの想いや行いがそのままこの世界の姿であるということです。私の中に暴力がある限り、この世界から暴力が絶えることはありませんし、私の中に慈悲があるとき、この世界は慈悲に満ちていきます。生きて何らかの行為を生み出す以上、私は自ら世界の生成に関与する主体として、そのすべてに責任を持たなければなりません。これに関しては誰かに代行してもらうことも、その責任を転嫁することもできないのです。その意味で、仏教の文脈が生後間もない釈尊の御口によって示そうとしたことは、まず「世界はこの私の投影なのだ」という自覚から始めなさいということだといえます。宗祖伝教大師によって提唱され、現在天台宗が中心的な事業として推進している「一隅を照らす運動」も、こうした自覚に基づく行為を奨励・実践していくものです。家庭や職場、また友人たちとの集いなど、あらゆる生活の場は私と世界との接点です。そこでもし、世界が良いものであってほしいと望むなら、まず自分自身の想いと行いを起点にすることです。私がいま立っている場所で“光”となることで、その“光”は確実にこの世界を満たしていくはずです。
|
|